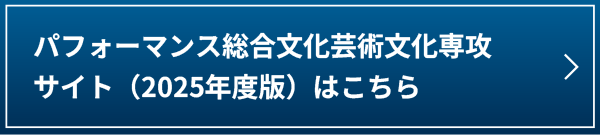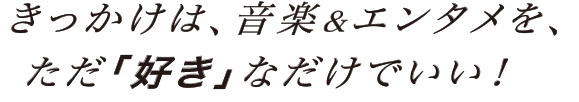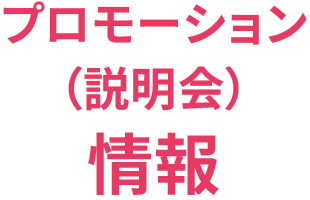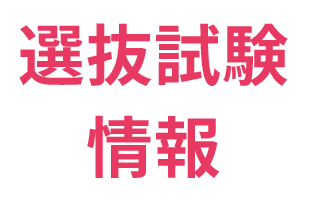音楽制作に特化した
「MDCC」の始動に向けて

PACSに新設される「MDCC(ミュージックデジタルコンテンツクリエーションクラス)」は、作・編曲家や音楽制作全般を目指す皆さんのためのクラスです。2027年4月の本格始動に先駆けて、2026年度から個人レッスンも開始。今回はMDCCならびに個人レッスンの講師を担当する作・編曲家の坪田修平先生に音楽やMDCCの魅力を語っていただきました。
今、なぜMDCCが求められるのか。
―現在の音楽業界では、作編曲、音楽制作でどのような知識、技能が求められていますか。

城之内:近年、DTM(デスクトップミュージック)といって、パソコンなどのアプリケーションを利用し、デジタルで曲を作る人が増えました。それに伴って、デジタル技能を身につけたい、という学生も増加しています。坪田先生は、アニメやゲーム音楽のクリエーターとして第一線で活躍していらっしゃいますので、業界の実情に照らし、作・編曲家などを目指す学生の指導にあたっていただきます。

坪田:僕の経験はおもにアニメやゲーム制作の現場になりますが、DTMで作編曲されている方は大勢います。DTM の知識は、その気になればネット上でも学べます。このクラスを目指す皆さんの中にも、すでにある程度デジタルで作曲ができる方もいるでしょう。でも、技術以外にも現場で求められることはたくさんあります。たとえばスタジオでレコーディングしたり、スタジオミュージシャンの方とお仕事をしたりするなかで、どうコミュニケーションをとれば円滑によい作品ができるのかなど、授業では、自分自身の経験をもとに、価値の高い情報を共有していきます。僕自身も、DTMで曲作りをし、現場で多くの人たちと関わり、時に怒られながら成長してきましたので、今度はその知識を皆さんに伝えていきたいです。
城之内:実は、DTMの普及で、現場で新たな問題なども発生しています。坪田先生がおっしゃったように、DTMの技術自体は、ある程度独学で身につけることは可能なんです。でも、クライアントの希望で、デジタルではなく生の楽器の音でレコーディングするケースも頻発します。その場合、DTMの曲をソフトの機能で楽譜に変換して、スタジオミュージシャンに演奏してもらうわけです。ところが、その譜面に結構派手なミスが生じるんです。これはDTM技術の問題ではなく、楽典の基礎知識がなければそのミスに気づくこともできないし、直すこともできません。そんな状態の楽譜をプロのスタジオミュージシャンに渡してしまう、というのでは、礼儀を欠いてしまいますよね。
坪田:僕も、これは現場で痛感しました。作・編曲家を目指すのであれば、打ち込みの知識があるだけでは、本当にだめなんです。逆に、譜面だけ書ければ良いか、と言えばそれもまた違う。さまざまな楽器の特性や音域、楽典の知識、DTM の技術、それらすべてがあってこそ、良い作品が作れます。DTM は、元を正せば楽器の代替手段であり、楽譜はミュージシャンとのコミュニケーション手段です。僕の場合は、ほかの方がDTM で作った曲の譜面化を依頼されることもあります。
城之内:作編曲を仕事として成立させるには、自己流では通用しなくなる壁が必ずあります。MDCCでは、そこを見越した授業を組み立てていきます。
作曲、編曲の魅力や、苦労
―先生方は、作曲、編曲のお仕事にどのような魅力を感じますか。

坪田:僕の場合は、作編曲は全て一人でこなしています。仕事をし始めて、自分が作曲した挿入歌がアニメで流れ、さらにスタッフロールに自分の名前を見つけたときは、嬉しかったですね。頑張ってよかったなと。映像に自分の音が合わさって1つの作品になる、そんな楽しさを味わうことができます。編曲だけを依頼されることも多いのですが、自分では思いつかないメロディーに出会えて面白いです。
城之内:編曲をする場合は、原曲へのリスペクトを大切にしています。メジャーなシンガーの方から「歌いやすかった」とか、「感情がこめられた」と言ってもらえると、アレンジの仕事も面白いなと感じます。自分のアルバムのために作る楽曲(作曲・編曲も兼ねている)は、1人のアーティストとして思い切り自由にやれる場合と、劇伴(ゲキバン)等のように「クライアントからの要望」で依頼者の求めに応え完成させる場合のものと、やりがいの方向性が異なりますね。
―お仕事で心掛けていることや、苦労はありますか。
坪田:毎回、前回より良いものを作ろうと心掛けています。メロディーの運び方、コード進行の流れ、音色の作り方、新しいソフトウェアの導入など、総合的に組み合わさって曲ができていく中で、どこか1つでも成長させようと思って取り組んでいます。
苦労というと、作曲のオーダーに対して考えすぎちゃう、という点ですかね。クライアントの要望を一通り聞いたら、一旦それを置いておいて、自分が単純にかっこいいな、と思うものを作るようにしています。得てして、そんなときの曲が一番出来がいいですね。

城之内:作曲を依頼されたら、どんなシチュエーションであっても何もないところから、全てを一人で完成させないといけない。誰も助けてくれません。だから、最初の一歩踏み出すのは本当に度胸がいります。加えて、クライアントの要望は実にさまざまで、出口が見えないこともあります。仕事なので、自分が好きな曲だけ書いて押し付けるわけにはいかない。一方、自分のインナーマインドにある音楽性は絶対に保っていないと、いつか心が疲弊してしまいます。ですから、アーティストである自分と、アルチザン(職人)である自分、この両軸を意識することが仕事として生き残るためには必須だと感じていますし、このバランス感覚を養うことを意識しています。
- 1
- 2